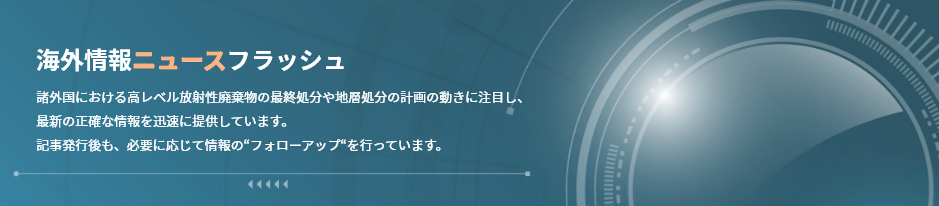
※海外情報ニュースフラッシュは、経済産業省資源エネルギー庁の委託事業として、公益財団法人 原子力環境整備促進・資金管理センターが提供しています。
最新記事
-
2025-12-22 《フランス》地層処分場の設置許可申請書に関する国家評価委員会(CNE)の報告書が公表
-
2025-12-17 《フランス》地層処分場の設置許可申請書の技術審査結果に関する規制機関の意見書が公表
 諸外国での高レベル放射性廃棄物処分
諸外国での高レベル放射性廃棄物処分
Learn from foreign experiences in HLW management
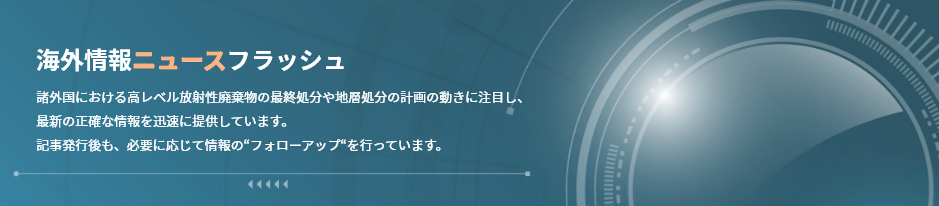
※海外情報ニュースフラッシュは、経済産業省資源エネルギー庁の委託事業として、公益財団法人 原子力環境整備促進・資金管理センターが提供しています。