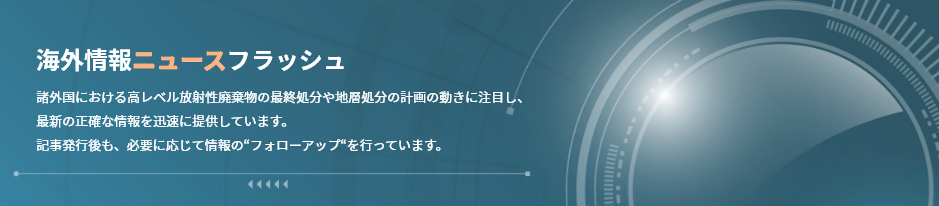
※海外情報ニュースフラッシュは、経済産業省資源エネルギー庁の委託事業として、公益財団法人 原子力環境整備促進・資金管理センターが提供しています。
 諸外国での高レベル放射性廃棄物処分
諸外国での高レベル放射性廃棄物処分
Learn from foreign experiences in HLW management
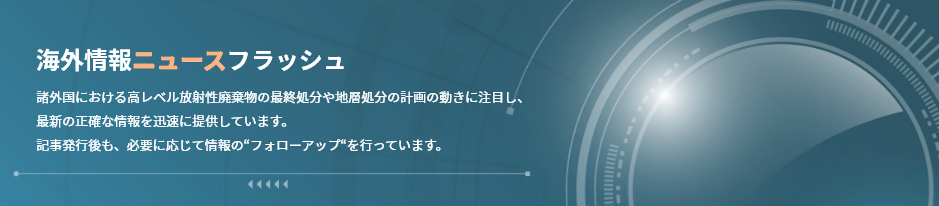
※海外情報ニュースフラッシュは、経済産業省資源エネルギー庁の委託事業として、公益財団法人 原子力環境整備促進・資金管理センターが提供しています。